👇 今すぐワインをチェックしたい方は、
オレンジワインを見る▶
AMBER REVOLUTION

ー目次ー
オレンジワインの原点は、約8000年前のジョージア(グルジア)にあります。この地域では、粘土でつくられた壺「クヴェヴリ」にぶどうを果皮ごと入れ、地中に埋めて自然発酵させる古い醸造法が受け継がれてきました。ワイン造りは飲み物の製造というより、自然の循環・宗教儀礼・家族や共同体の営みと深く結びついた行為であり、そこには「人は自然とともに生きる」という価値観が息づいていました。
この古代の醸造法は時代とともにヨーロッパ各地へ伝わり、徐々に姿を変えながらも、長いあいだワイン文化の根底に残り続けました。しかし20世紀に入ると、近代技術の発展によって、透明でクリーンな白ワインが国際基準となり、果皮を使う伝統的な醸造はごく限られた地域を除いて姿を消していきます。それでもジョージアでは、クヴェヴリ醸造の哲学が家庭や地域共同体の中で守られてきました。
20世紀末、この古代のアプローチはイタリア北東部フリウリ(コッリオ/Collio)と、国境を接するスロヴェニア西部ゴリシカ・ブルダ(ブルダ/Brda)の造り手たちによって再び注目されます。彼らが見つめ直したのは、「ぶどうそのものの力を、できるだけ誠実に、過剰な操作をせずに表現したい」という問いでした。これが後に「オレンジワイン革命」と呼ばれる大きなうねりの出発点となるのです。

HISTORY OF ORANGE WINE
BC6000〜|古代ジョージア
クヴェヴリによる壺醸造が行われ、ぶどうを果皮ごと自然発酵させる技法が成立。ワインは自然の循環・共同体・儀礼と結びついた生活文化として存在した。
中世〜近世|ヨーロッパ
修道院を中心にワイン造りが体系化され、保存性・運搬性・安定性が重視される時代へ。果皮を使う白ワインは徐々に姿を消し、地域の家庭にわずかに残るのみとなる
19〜20世紀|近代ワインの確立
近代醸造学の発展により「透明・クリーン・短期出荷型」の白ワインが国際的スタンダードに。果皮による醸した白は少数地域を除き大きく衰退する。
1990年代|フリウリ・ブルダの再発見
清澄・濾過・すぐ飲める白ワインへの疑問が生まれ、ぶどうをより自然に表現する方法としてスキンコンタクトが再評価される。ラディコンやグラヴナー、スロヴェニアのモヴィア、ムレチニクらが中心的役割を担う。
1997〜2005|ジョージアへの回帰
グラヴナーがジョージアを訪問し、クヴェヴリ醸造の哲学に触れる。この経験はフリウリとブルダの造り手に大きな刺激となり、「自然の働きを尊重する」という価値観の再発見へ繋がる。
2004年|「オレンジワイン」命名
英国のワイン商デヴィッド・A・ハーヴェイが “Orange Wine” と命名。白と赤の間で説明しにくかったスキンコンタクト白を示す用語として広まり、国際的にジャンルが可視化される。
2010年〜現在|世界への広がりと成熟
自然派ワインの高まりとともに世界で注目度が上昇。味わいだけでなく「どのような考え方で造られているか」が評価軸となり、多様性と成熟が進むフェーズへ。
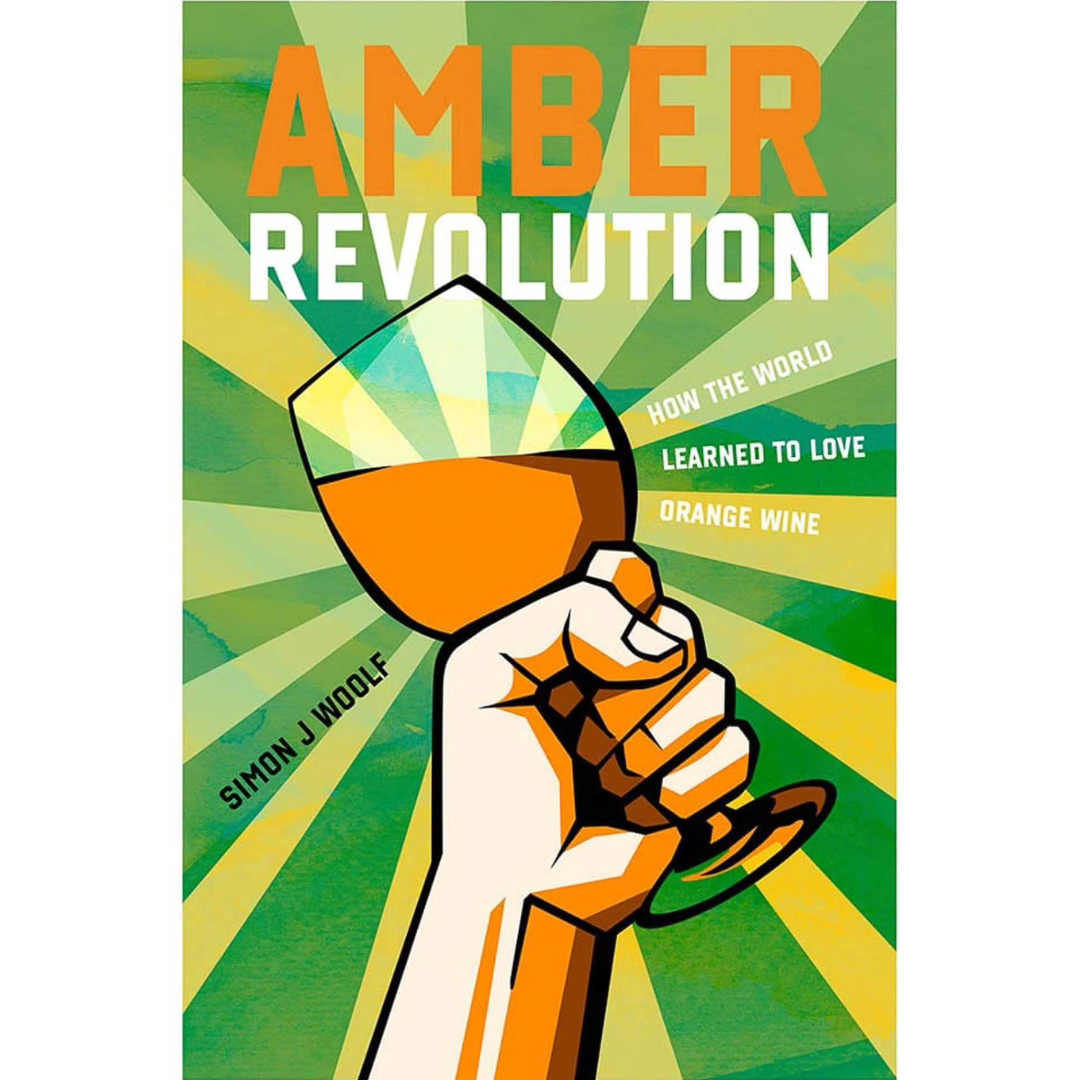
ここからは実際に起きた「オレンジワイン革命」を
ノンフィクション小説でお送りします。
AMBER REVOLUTION STORY
フリウリ&スロヴェニアの丘から世界が変った
1990年代の終わり。冬の霧が沈むフリウリ・コッリオの丘と、それに連なるスロヴェニア・ブルダの丘で、誰も気づかない「価値観の揺らぎ」が起きた。当時の白ワインの常識は明確だった。
- 透明であること
- クリーンであること
- 雑味がないこと
- 若いうちに出荷されること
この「透明こそ正義」という常識のもと、濾過や清澄、培養酵母、温度管理が徹底され、世界中の市場がそれを求めていた。だが、その時代の最前線にいたフリウリの生産者たちは、ある違和感に気付いた。
「どこの畑で育ったのかわからないワインになった。」
テロワールを尊重してきた土地だからこそ、“ぶどうの声の消失” は深刻な矛盾として上がった。この疑問がのちに世界の価値観を揺るがす「オレンジワイン革命」の火種となる。

フリウリ・コッリオ(イタリア)と、国境を挟んで隣接するスロヴェニア・ブルダは、政治的には2つの国に属しながら、歴史的にも文化的にも完全に地続きのワイン文化圏だった。
- 同じ土壌(ポンカ/オポカ)
- 同じぶどう(例:リボッラ=レブラ、フリウラーノ)
- 同じ栽培文化
- 同じ丘陵地帯の連続性
第二次世界大戦後、国境が引かれたものの、地域の人々にとって丘は常に「ひとつの世界」。土地の記憶・伝統・家族の歴史が2つに分けられたに過ぎなかった。だからこそ、“本来のぶどうの姿とは何か”という問いが、国境をまたいで行き交った。
イタリア側のコッリオ、スロヴェニア側のブルダ、さらに思想的支柱として両国のカルスト地方、伝統の残るヴィパーヴァ谷。これらが、後の革命の舞台となる。
 イタリア・フリウリ側の丘:コッリオのぶどう畑(秋)
イタリア・フリウリ側の丘:コッリオのぶどう畑(秋) スロヴェニア側の丘:ブルダのぶどう畑(秋)
スロヴェニア側の丘:ブルダのぶどう畑(秋)1980〜1990年代、フリウリの白ワインは世界的ブームになった。だがその成功は、皮肉にも大きな影響を与えていた。
- 淡いイエローゴールド
- 完全に澄んだ外観
- 酸化の影を徹底的に排除
- 早飲みスタイルの大量生産化
技術は進歩しワインは洗練された。しかし同時に、ぶどうの複雑さも、土壌の個性も、醸造家の哲学も薄まっていった。ヨスコ・グラヴナーは後にこう語る。
「技術はワインを透明にしたが、その本質を濁した。」
この地域の生産者は、ワインを“土地と人の共同体の記憶”と捉える文化を持つ。その文化の根幹が失われつつあるという危機感が、大きな転機を生んでいく。

1990年代後半、ラディコンは徹底的に考え続けた。
- なぜ濁ってはいけないのか
- なぜ透明でなければいけないのか
- 皮は本来ワインの重要な一部ではないのか
そして彼はひとつの答えにたどり着く。
「ぶどうの力は皮に宿っている。」
マーケットは敵に回る。仲間からは「時代遅れだ」と笑われる。輸出は減り収入も落ちる。それでも彼はやめなかった。

グラヴナーはさらに鮮烈だった。世界的な評価を受け、高価格帯ワインをリードする醸造家。そんな彼が自分の白ワインの全部を捨てた。そしてジョージアへ飛び、クヴェヴリと“自然に委ねるワイン造り”に出会う。
「私ではなく、自然がワインをつくる。」
帰国後、彼は迷わず全てを変えた。
- クヴェヴリ導入
- 果皮・種・果梗ごと発酵
- 地中での長期熟成
- 濾過も清澄もしない
- 市場の需要を無視する
当然、理解されない。批評家は酷評する。レストランは扱わない。地元の審査会でも評価されない。 革命の初期は、孤独と批判で10年連続の赤字だった。

オレンジワイン革命は「コッリオの2人とブルダの仲間が突然起こした」のではない。 同じ時代、同じ空気を吸いながら、カルスト(Carso/Kras)やヴィパーヴァ谷にも 哲学的な潮流が広がっていた。
- Čotar / チョタル
- Zidarich / ジダリッチ
- Edi Kante / エディ・カンテ
彼らは全員が“オレンジワインの長期醸し”をしたわけではない。 しかし思想は同じだった。
- テクニックより畑
- 自然に逆らわない
- 土地に敬意を払う
- 透明度などどうでもいい
- 長い熟成による“土地の記憶”の表現
これらの考え方は、ラディコンやグラヴナーの背中を押す 精神的な土台となった。
ここには古くから“皮ごと醸す伝統”が残っていた。 その存在は、「皮ごと醸すことは異端ではない」という確かな根拠となり、 革命を地域全体のムーブメントへ押し上げていった。
イギリスのワイン商デヴィッド・A・ハーヴェイが放った一言、“Orange Wine”。 たったそれだけで、世界のワイン産業はこのカテゴリーを“認識”した。 それまでは「奇妙な白ワイン」だったものが、名称を得た瞬間からジャンルになった。
- 輸入業者が取り扱い始める
- メディアが取り上げる
- 生産者が互いを知り始める
- 消費者が検索できるジャンルになる
命名は革命の“見えないガソリン”だった。

革命の初期、ラディコンもグラヴナーもモヴィア/MOVIAも、ほぼ全員が失敗と孤立を経験している。
批評
- 「酸化している」
- 「汚れている」
- 「欠陥ワイン」
- 「理解不能」
市場
- 国内でも売れない
- 他国への輸出が止まる
- ソムリエが扱いたがらない
- レストランで拒否される
仲間の反応
- 「どうかしている」
- 「古臭いやり方」
- 「金にならない」
実際の生活
- 赤字が続いた
- 設備投資が重くのしかかる
- 家族から心配される
- 周囲から理解されない
これらは誇張ではなく、実際にあった“革命の代償”だ。だが、この苦難はすべて「本物とは何か」という問いを追求した結果だった。そして、その答えに世界が気づくのは、もう少し先の話になる。

2010年代以降、自然派ワインの潮流とともにオレンジワインは世界的ムーブメントとなった。しかし、ブームという言葉で片付けるのは誤りだ。
- 長期醸しの伝統の再評価
- 皮ごと発酵の科学的見直し
- テロワール重視の流れ
- 人が自然に寄り添う思想
- 市場の透明至上主義からの脱却
これらは単なる技法や流行ではなく、価値観そのもののアップデートだった。今日のオレンジワインは長期醸しだけではなく、多様なスタイルが生まれた。しかし根底には、革命初期の造り手たちと同じ問いがある。
「ワインとは、誰のものか。」
「自然と人は、どのように共にあるべきか。」
こうした問いに世界の飲み手が少しずつ目を向けはじめた一方で、ブームは別の現実も生み出していく。“市場のためのオレンジワイン”が大量に生まれたのである。
醸しの日数を数日追加し、色味だけをそれらしく仕立てたワイン。トレンドに合わせ、短期間で商業的に仕上げたワイン。背景に哲学も思想もなく、ただ「売れるから生産する」ためのオレンジワイン。
もちろん、それら全てを否定する必要はない。ワインの世界が広がり、多様性が生まれるのは歓迎すべきことだ。しかし、本物の哲学でワインをつくる人々にとって、工業的なオレンジワインと同じ棚に並び、同列に扱われる状況には、大きな戸惑いも生んでいる。
- 手法だけ模倣したワインが世界に溢れる
- 工業品とクラフト品が店頭で同じ棚に並ぶ
- 色の濃さだけで「本格的」と誤解される
- 消費者の体験が混乱し、本物の価値が見えづらい
それでも彼らは、声高には批判しない。なぜなら、多様性そのものが文化を進化させることを知っているからだ。ブームが生んだ光と影。その両方を引き受けながら、オレンジワインは次の段階へと進んでいく。

1990年代後半、透明でクリーンな白ワインが世界を席巻していた時代に、果皮ごと醸す白ワインを造ることは、単なる逆行ではなく“孤独な闘い”だった。批評家には理解されず、市場はほとんど反応せず、地元でも「時代遅れ」と言われ、ワイナリーは赤字に沈む。それでも彼らは、手法を守ったのではない。
価値観を守ったのだ。
- 本物のぶどうの味とは何か
- 土地の記憶はどこに宿るのか
- 自然の働きをどう受け止めるべきか
- 人はワインに“何を求めているのか”
その問いに対し皮ごと醸す行為は、最も誠実な答えのひとつだった。そしてその答えは、市場の流行とは無関係に、静かに積み重ねられていった。フリウリ、ブルダ、カルスト、ヴィパーヴァ。オレンジワイン革命の源流となった地域の造り手たちは、誰もが同じ言葉を口にする。
「色ではなく、思想だ。」
実際、スロヴェニアの名門 カバイ/KABAJ を訪れた際、ジャン・ミッシェル・モレルが問いかけた。
「本物のワインとは何だ。貴方はどう考えるのか。」
この問いには正解がない。だからこそ、造り手は迷いながら、信じる道を進む。果皮を使う意味。自然の働きをどれほど受け入れるか。土地の記憶をどこまでワインに預けるか。人は醸造にどれほど手を加えるべきなのか。
オレンジワインを造ることは、技法ではなく「ぶどうと自然との向き合い方」を問う行為そのものだ。では何が、“本物のオレンジワイン” なのか。その答えは、技術的な定義ではなく、造り手の在り方に宿る。
- ぶどうの生命力に敬意を払う
- 土地の記憶を大切にする
- 流行ではなく、信念によって醸す
- 目に見えない時間と手間を惜しまない
- 自然と人の共作であることを理解している
そしてなにより、「こうあるべき」ではなく「こうありたい」でワインと向き合う姿勢が、本物をかたちづくる。哲学なき“オレンジ色”がある一方で、自分たちの信じるオレンジワインを造り続ける人々がいる。その緊張した関係こそが、このジャンルをより豊かで複雑なものにしている。

ラディコンやグラヴナーの時代で革命が終わったわけではない。フリウリやブルダの若い造り手たちも、次の問いを立て続けている。
- 環境変動に対しオレンジワインはどう進化すべきか
- 醸しの意味をもう一度問い直す必要はないか
- 土地の個性をどう未来へ繋げるか
- 消費者に「背景」を正しく届けるにはどうすべきか
そしてこの革命は、造り手だけのものではない。飲み手が「背景を知ろうとする」ことで、文化が成熟する。理解する人が増えれば、哲学あるワインは必ず生き残る。流行は去っても、思想は残り続ける。オレンジワインの未来に必要なのは、新しい技術でも、強烈なカリスマでもない。「本質を問い続ける姿勢」だ。
オレンジワインはただのワインではない。土地の記憶であり、自然の息づかいであり、造り手たちの信念そのものだ。そしてその信念こそが、この革命を“文化”として未来へ繋いでいく。紛れもなくその姿勢は、フリウリ・ブルダの丘でも、カルストの石灰岩でも、ジョージアのクヴェヴリの底でも静かに脈打っている。
オレンジワイン革命とは、「古代の復活」や「醸しの手法」や「色」でもなく、要は「向き合い方」なのだ。“ワインの本質を取り戻す”、“人間が自然とどう生きるかをもう一度考える” ための長い旅だ。
そしてこの旅は、今も続いている。
造り手と、私たち飲み手によって。

オレンジワインの物語をたどると、色やスタイルの違いよりも、「どんな価値観で造られているか」が大切だと気づきます。8000年の歴史、フリウリやスロヴェニアの丘、そして今も続く造り手たちの問いかけ。その背景を少し知るだけで、グラスの中の一杯は、また別の表情を見せてくれます。
次にオレンジワインを選ぶ時、「どんな人が造っているのか」「どんな思想で醸しているのか」を少し想像して頂けたらと思います。それはきっと、造り手たちが命がけで守ってきた“革命の続き”に、いち飲み手として参加することでもあります。【哲学編】を読んだ貴方なら、もうオレンジワインの一杯が、ただの「流行ワイン」ではなく、小さな物語に見えているはずです。ここから先は、ぜひグラスの中で、その続きを確かめてみて下さい。
※本稿は上記の一次・二次資料および現地関係者への取材をもとに、365wine(株)が独自に編集・再構成したものです。





